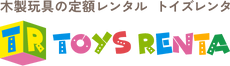積み木は昔から愛され続ける伝統的なおもちゃ。生後まもない赤ちゃんから小学生まで何歳になっても遊べます。自由度の高いおもちゃなので、積む以外にも遊び方の幅を広げ、五感を刺激してあげたいですよね。
このページでは、成長が著しい0歳から4歳の時期に焦点を当て、おすすめの積み木遊びと基本的なねらい、大人の関わり方を紹介します。
【年齢別】積み木のおすすめの遊び方
積み木の遊び方のアイデアを、年齢別に紹介します。お子さまの年齢に合わせて、積み木の遊び方を参考にしてくださいね。
0歳
0歳は、身体感覚の基礎が作られる時期です。遊ぶというよりも、口に入れたり触ったりする動作を通して、五感をフルに使っています。親子の愛着形成が重視される時期でもあるので、「まるいね」「赤い積み木だね」と声をかけながら遊ぶのも良いでしょう。
お座りできる月齢になると、ママやパパが積んだ積み木を崩して遊ぶこともしばしばあります。積み木が音を立てて崩れたり、違う形になったりするのを見るのは、赤ちゃんにとって刺激的なようです。
1歳
積み木を少しずつ積めるようになる目安は、1歳前後です。同じ色の積み木を並べてみたり、大小さまざまなサイズの積み木を積んでみたりして、遊びながら大きさや色の違いを学んでいます。
また、積み木のパーツを電話に見立ててごっこ遊びもできるようになる時期です。赤ちゃんの頃に比べると、いろいろな遊び方ができるようになります。
2歳
2歳は遊びの幅がぐっと広がる時期です。積み上げ方は1歳の頃に比べると大胆になったり、慎重に積み上げたりと個性が表れる時期でもあります。また、お友だちやきょうだいの遊びを真似したくなる頃です。ご両親も一緒に積み木を楽しみ、高く積み上がったときは「大きいね」などと声かけして言葉で表現してみましょう。
3歳
3歳になると、ほかのものと組み合わせ、遊びを発展させられるようになります。家を作ったり道路や線路に見立てて車を走らせたりして、アイデアをどんどん形にしてみましょう。イメージしたものを形にすることで、豊かな表現力・想像力が育まれます。
4歳
4歳は、自ら目的を持って遊べるようになる時期です。手先が器用になって自分の考えたルールで想像しながら高く積んだり、バランスを工夫して積んだりできるようになります。
また、積む以外に見立てて遊ぶのが上手になるのもこの時期です。人形や車などのおもちゃと積み木を組み合わせて遊ぶ子もいます。
積み木遊びのねらい
積み木はさまざまな遊び方ができますが、それぞれの遊び方にはねらいがあります。遊び方によって、どのような力が身に付くのかを見ていきましょう。
にぎる・なめる
にぎったりなめたりする動作も、赤ちゃんにとっては立派な遊びです。触った感触や味、香りを通して、五感に良い刺激を与えます。また、ものの形や大きさも手や口を通して少しずつ認識しています。
音を鳴らす
積み木同士をぶつけ合って音を鳴らすのも、遊び方の1つです。ぶつける位置によって音が変わり、聞き分ける力が養われるでしょう。パーツごとに、異なる音が出るしかけが施された積み木もあります。
崩す
積み木を崩す遊び方は、ものが落ちていく動きや音を楽しむのがねらいの1つです。壊れやすい部分と崩しやすい位置を見つけと、設計の基礎を学べます。また、崩れても、もう一度チャレンジしようとする意欲も育まれるでしょう。
積む
積み木を高く積む遊び方は、自分の力で高く積む楽しさと達成感を知ることができます。バランス感覚や集中力、手先の微妙な力加減が身につきます。
分類する
カラーや形などの共通点を見つけて、ジャンルごとに分ける遊び方は集中力を育み、色・ものの名前や形を覚えられます。
形を作る
積み木で自分の好きなものを作る遊び方は思考力や創造性、手指の動きなど、あらゆる感覚を思う存分使います。
ごっこ遊び
まとめ
積み木は年齢ごとに推奨の遊び方がありますが、やりたいように遊ばせるのが大前提です。大人では思いつかないような意外な遊び方が、お子様にとっては学びになります。
特に木製の積み木は独特の質感やにおい、木目の美しさなどお子様の五感を刺激する要素がたっぷりです。シンプルなデザイン故に、遊び方が限定されず、想像力が刺激されます。
お子さまにもっと気軽に、良質な木のおもちゃに触れさせてあげたいとお考えの方は、おもちゃのサブスクを検討してみてはいかがでしょうか。トイズレンタはお子さまの発達や月齢にぴったりの木のおもちゃをお届けいたします。