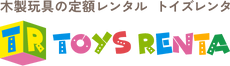公園や保育園でのおもちゃの取り合いを見たとき、親としてどう対応すればいいか悩むことはありませんか。「順番にね」と言ってもすぐには伝わらず、困った経験がある方も多いのではないでしょうか。「貸して」「どうぞ」と言える子どもに育ってほしい——多くの親が願うことですが、実際にはどうすれば自然にその言葉が出てくるのでしょうか。幼児期の子どもは、自分の欲求を優先しがちで、他者との関わりに戸惑うことも少なくありません。しかし次第に他の子どもと関わりながら「協力する」「順番を守る」「相手の気持ちを考える」といったスキルを身につけていきます。こういった学びの鍵となるのが、遊びの時間でしょう。特におもちゃを使った遊びの中で、子どもたちは楽しみながら自然に「貸して」「どうぞ」といった協力の感覚を育んでいきます。
では、具体的にどのような場面でこの力が育まれるのでしょうか。
0〜4歳の発達段階における協力の学び

2歳頃:おもちゃはまだ「自分のもの」
2歳前後の子どもは「自分のもの」「自分の世界」という意識が強く、興味を持ったおもちゃを独占しがちです。この時期の子どもにとって、おもちゃを貸すことは「取られる」と感じることが多く、「相手のために譲る」という考えはまだ十分に発達していません。しかしこれはわがままではなく、自己主張の一環であり、成長の証ともいえます。この時期に親ができることは、貸し借りの経験を少しずつ積ませることです。「ママにも貸してくれる?」「順番こしようね」と優しく声をかけることで、子どもは「貸すこと」が特別なことでないと認識し始めます。最初は難しくても、親が「ありがとう、うれしいな!」と伝えることで、貸すことへのポジティブな経験を積んでいくことができます。
3歳頃:他人の気持ちを知りはじめる
3歳を過ぎると、子どもは少しずつ他者の気持ちを理解し始めます。まだ完全に「相手のために」とは思えないことも多いですが、「お友だちにも使わせてあげようね」といった声掛けが少しずつ伝わるようになります。公園で遊んでいるときに、「○○ちゃんも遊びたいみたいだね。順番こできるかな?」と声をかけると、貸すことへの意識が芽生えてきます。この時期には「貸したらまた自分のところに戻ってくる」ことを理解できるようになると、少しずつ貸し借りがスムーズになります。無理に強制するのではなく、「お友だちが遊び終わったら、また○○ちゃんの番だよ」と安心感を持たせることが大切です。
4歳頃:社会性が発達する時期
4歳になると友だちとの関わりの中で、「順番を待つ」「相手に貸す」といった行動が自然に見られるようになります。遊びのルールを理解し始め、「一緒に遊ぶことの楽しさ」を感じることが増えるため、貸し借りもスムーズに進むことが多くなります。この頃には「お友だちが使い終わったら○○ちゃんの番だね」「一緒に使うと楽しいね」といった声掛けがより効果的になります。また親が「交代」や「協力」を実践することで、子どもも自然に学んでいきます。
おもちゃ遊びが協力を学ぶ場になる理由

おもちゃ遊びは、子どもが他者と関わるための重要な機会となります。例えば以下のような遊びの場面で、自然と協力のスキルが育まれます。
積み木遊び:一緒に大きな塔を作る過程で、「ここに積んでいい?」「もっと高くしよう!」といったやり取りが生まれます。この中で子どもは順番を守ることや、相手のアイデアを尊重することを学びます。積んだブロックが崩れた時もチャンスです。「大丈夫、もう一回作ろう」と励まし合う経験を通じて、相手への思いやりの気持ちも育まれます。
おままごと:お料理ごっこでは「ジュースを作ったからどうぞ」「次はサラダ作ってね」などの会話が生まれます。子ども同士が役割を決めて協力しながら遊ぶことで、「相手のために動く」ことの楽しさを実感しやすくなります。
電車や車のコース遊び:レールをつなげたり、道路を作ったりする遊びでは、「ここにつなげてみよう」「こっちの道を長くしよう」と協力しながら遊ぶ機会が生まれます。順番を待ったり、相手の作ったものを壊さずに尊重することを学ぶことができます。
パズルや共同制作の遊び:大きなパズルを一緒に完成させたり、絵を共同で描いたりすることで、「この部分は○○ちゃんがやってね」「次はここに貼ろう」といった協力の経験が生まれます。達成感を共有することで、チームワークの楽しさを味わえます。
ボードゲームやルールのある遊び:簡単なすごろくやカードゲームを取り入れると、順番を守ることや勝ち負けの概念を学ぶきっかけになります。負けた時に「次は勝てるかも!」と励ますことで、ルールを守る大切さや相手を思いやる気持ちを育てられます。
このように子どもが楽しみながら協力する経験を積むことで、自然と社会性が育まれていきます。
トラブルも学びのチャンスに

子ども同士の遊びでは、時にはおもちゃの取り合いやケンカが起こることもあります。しかし、これらのトラブルは社会性を学ぶ絶好の機会です。親がすぐに介入して解決するのではなく、子ども同士で話し合ったり、お互いの気持ちを理解する手助けをすることが大切です。例えば「○○ちゃんも遊びたかったんだね」「じゃあ、どうしたらいいかな?」と問いかけることで、子ども自身に考えさせることができます。時には「一緒に使う」「交代で遊ぶ」「別のおもちゃを使う」といった解決策を子どもが見つけることもあります。このような経験を積み重ねることで、相手を思いやる気持ちや、自分の気持ちを伝える力が育まれていきます。また子どもが感情的になったときには、親が冷静に状況を整理し、「○○ちゃんが遊びたかった気持ちもわかるし、△△ちゃんも使いたかったんだね」と気持ちを言語化してあげるのも有効です。こうしたサポートを続けることで、子どもは自分の気持ちを言葉で表現し、適切に解決する力を養っていきます。
親の関わりが子どもの協力心を育む

親の関わり方によって、子どもの貸し借りへの姿勢は大きく変わります。ただ「貸してあげなさい」と指示するのではなく、親自身が協力の見本を示すことが大切です。例を挙げると、おもちゃを使っている子どもに「ママも少し使ってみてもいい?」と尋ね、「ありがとう!」と感謝を伝えてみましょう。貸し借りがポジティブなものだと認識しやすくなります。さらに親が子どもと一緒に遊ぶ中で、「交代する」「役割を分担する」といった経験を増やすことで、自然と協力の大切さを学んでいきます。遊びの中で少しずつ社会性を育んでいくことが、将来的な対人関係の基礎となるのです。
最後に:遊びを通じて協力の心を育もう
子どもたちにとって、「貸して」「どうぞ」は、ただの言葉ではなく、思いやりや協力の第一歩です。最初はうまくいかないこともあるかもしれません。でも、小さなやり取りを積み重ねることで、「一緒に遊ぶって楽しい」「相手を大切にするって気持ちがいい」と感じられるようになっていきます。おもちゃを通じた小さなやり取りが、やがて子どもの大きな成長につながり、思いやりあふれる未来を築いていきます。親子で楽しみながら、その温かい瞬間をたくさん積み重ねていきましょう。